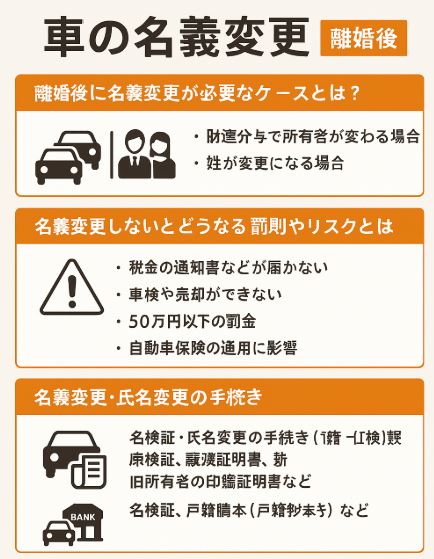目次
13年以上経過した車を手放すと補助金がもらえる?基本制度をわかりやすく解説
13年以上同じ車に乗り続けている方にとって、「そろそろ買い替え時かもしれない」と感じるタイミングは、税金の重課や車検費用の増加、燃費の悪化など、さまざまな負担が重なる瞬間です。そんな中、「13年以上経った車を手放すと補助金がもらえるのか?」という疑問を持つ方も多いはずです。この章では、13年経過車と補助金の関係性、過去の制度、そして2025年時点で考えられる支援策の概要をわかりやすく解説します。
買いたい人必見! 市場に出ない【お得】な中古車!
高く売りたい人必見!車一括査定で価格比較!
なぜ「13年」が区切りになるのか?
まず、なぜ「13年」が制度上の節目になるのでしょうか。その背景には、日本政府が進めてきた「グリーン化政策」が関係しています。古い車は排出ガスや燃費性能の面で、現在の新車と比べるとどうしても環境負荷が高い傾向にあります。そのため、政府は環境性能の低い車を買い替えさせ、燃費や排出ガス性能の良い車に乗り換えてもらうことを目的として、一定の年数を経過した車に対して税制上の「重課」や、「補助金付きの買い替え優遇」を設けているのです。
特に「13年」という年数は、2009年からスタートした「エコカー補助金制度」でも、基準年数として扱われてきました。この制度では、13年以上経過した車を廃車にしてエコカーに乗り換えると、10万円程度の補助金が支給されるという内容が大きな話題となりました。
過去の「エコカー補助金制度」との関係
2009年〜2010年にかけて実施された「エコカー補助金」は、13年超の車の買い替え促進に大きな効果をもたらしました。該当する車両を廃車にして、一定基準を満たしたエコカーを購入することで、最大25万円(商用車の場合)の補助金が支給される仕組みでした。この制度は、経済対策と環境政策の両立を狙った一時的な施策でしたが、多くの人が利用しました。
2025年現在、当時と同じ補助金が再び実施されているわけではありませんが、その考え方は継承されています。たとえば「グリーン化特例」や「CEV補助金(クリーンエネルギー自動車補助金)」などの制度に反映されており、13年以上経過したガソリン車をEVやPHEV、FCVに乗り換えると、優遇措置を受けられる場合があります。
2025年現在、何が使えるの?
具体的に、2025年時点で13年超の車を買い替える際に活用できる支援策には以下のようなものがあります。
-
グリーン化特例(環境性能割):13年を超えたガソリン車・ディーゼル車には税の加重措置がある一方、電気自動車や低排出ガス車に買い替えた場合、環境性能割の非課税や軽減措置が受けられます。
-
CEV補助金:経済産業省が主導するクリーンエネルギー車向けの補助制度。EV・PHV・FCVを購入すると、車種ごとに10万円〜85万円程度の補助金が設定されています。
-
地方自治体による独自の買い替え補助:東京都や神奈川県など一部の自治体では、13年を超えた車の買い替えに対して独自の補助制度を実施しているところもあります。例として、東京都ではEV購入で最大60万円の補助金が出る制度があり、13年以上経過した車を廃車にした場合に限って対象になるケースもあります。
注意したいポイント
補助金は「誰でも自動的にもらえるもの」ではありません。対象となる車種、購入先、申請タイミング、廃車証明の提出など、条件が細かく決められています。とくに13年以上の車を手放すことを条件としている制度では、廃車証明(リサイクル券の提出を含む)などが必要になるケースがほとんどです。
また、補助金は年度ごとに予算が決まっており、予算消化により早期終了することもあるため、制度を活用するには「いつ・どんな制度があるか」を事前に調査しておくことが重要です。
13年以上経過した車の買い替えには、補助金や税優遇制度を活用できるチャンスがあります。特に「環境性能の良い車」に乗り換えることで、負担を軽くしながらエコにも貢献できます。制度は国だけでなく自治体にもあるため、まずは自分の住んでいる地域の支援策を確認することが、賢い買い替えの第一歩と言えるでしょう。
グリーン化特例ってなに?13年超の車が重課税される仕組みとその回避方法
13年以上経過した車を保有していると、「車検のたびに税金が高くなった気がする…」と感じることがあるかもしれません。これは気のせいではなく、日本の税制の中にある「グリーン化特例(旧環境対応車普及促進税制)」による影響です。この制度は一見すると複雑に見えますが、基本を押さえることで負担を減らす手段が見えてきます。
この章では、グリーン化特例の仕組みとその対象、さらに13年超の車が受ける“重課税”の具体的な内容と、それを回避するための現実的な選択肢をわかりやすく解説します。
グリーン化特例とは?
「グリーン化特例」は、車の環境性能に応じて税負担を調整する制度で、正式名称を「自動車税種別割及び自動車重量税の環境性能割」といいます。環境に配慮した車には税の軽減や非課税の恩恵が与えられる一方で、環境性能が低い車(特に古い年式のガソリン車など)には“重課”という形で税金が上乗せされます。
この制度は「税によるインセンティブ(動機付け)」の典型的な例であり、「エコな車に乗り換えてもらうことでCO₂排出を減らす」ことを狙いとしています。
13年以上経過した車への影響とは?
問題となるのがこの「重課」部分です。登録から13年を経過したガソリン車・ディーゼル車などは、毎年の自動車税および車検時に支払う自動車重量税が上がります。
【自動車税(種別割)の重課】
-
通常:排気量ごとに定められた金額(例:1500cc → 約34,500円)
-
13年超:おおむね15%重課(例:1500cc → 約39,700円)
【自動車重量税の重課(車検時に発生)】
-
通常:0.5tあたり6,600円(2年分)
-
13年超:0.5tあたり8,200円(約25%増)
-
18年超:0.5tあたり8,800円にさらに増額(さらに約33%増)
たとえば、車重1.5tの普通車を13年以上保有している場合、車検ごとの重量税だけで4,000円以上余分にかかる計算になります。また、自動車税と合わせると年間で6,000~8,000円程度の追加出費となるケースが多く、車を長く乗ることが決して“経済的”とは言い切れなくなるのが現実です。
ハイブリッド車・電気自動車には“優遇”がある
一方で、環境性能に優れた車に乗り換えると、これらの税負担は軽減されます。
-
電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV):自動車重量税が「免税」または「非課税」
-
ハイブリッド車(HEV):要件を満たせば最大75%軽減されるケースもあり
-
軽自動車でも新車であれば:環境性能により1〜2年間の税軽減対象になることも
つまり、古い車を持ち続けると増税、新しい車(特にエコカー)に乗り換えると減税という、税制の仕組み上、「乗り換えた方がトータルで安くなる可能性が高い」という構造ができているのです。
重課を避けるには?3つの方法
ここでは、13年超の車にかかる重課を回避するための具体的な方法を紹介します。
方法①:13年を迎える前に買い替える
最も確実で簡単な方法がこれです。12年目など、まだ重課が適用されていないうちに買い替えを検討すれば、税負担の増加を未然に防げます。とくに車検が近いタイミングで13年を迎える場合は要注意です。
方法②:エコカーに乗り換える(補助金と併用可能)
電気自動車やハイブリッド車などに買い替えれば、重課を回避するどころか税軽減や補助金対象にもなります。CEV補助金や自治体の支援制度と組み合わせると、初期費用の負担も軽くなる可能性があります。
方法③:軽自動車にダウンサイジング
軽自動車はもともと税負担が少ないですが、13年を超えるとこちらも重課対象になります。それでも普通車よりは負担が少ないため、「税負担を抑える」という観点では有効な選択肢です。
今後の法改正にも注意
グリーン化特例は、時代に応じて見直しが行われています。たとえば、環境性能の基準は年々厳格化しており、将来的には現在のハイブリッド車ですら優遇対象から外れる可能性もあります。2025年以降、政府がより本格的に「脱炭素社会」にシフトしていく中で、EVへの買い替え促進策がさらに強化されることも十分にあり得ます。
そのため、今後も「自分の車がどの税制区分に属するのか」「優遇を受けられるかどうか」は定期的に確認することが大切です。
13年以上経過した車は、グリーン化特例により税金が高くなる「重課税」の対象となります。この制度は、エコカーへの買い替えを促す政策の一環です。負担を回避するには早めの買い替え、環境性能の高い車への乗り換えが効果的。補助金制度とも連動させることで、さらにお得に買い替えを進められます。
2025年時点で使える補助金・優遇制度一覧(国・自治体別に整理)
13年以上経過した車を買い替えようと考えている方にとって、購入時の出費を抑える補助金や税制優遇は非常に重要な情報です。特に2025年現在、国の制度と地方自治体の制度が併用できるケースもあり、条件をしっかり確認することで数十万円の支援を受けられる可能性もあります。
このセクションでは、2025年5月時点で利用可能な主要な補助金制度と税制優遇について、国の制度と自治体の制度に分けて詳しく紹介します。
国の補助金制度
まずは国レベルで実施されている代表的な補助金や優遇制度を紹介します。
① CEV補助金(クリーンエネルギー自動車補助金)
経済産業省と環境省が主導する制度で、EV(電気自動車)・PHEV(プラグインハイブリッド)・FCV(燃料電池車)などを対象としています。
-
対象車種:補助金対象に登録されたEV/PHEV/FCV
-
補助金額の目安(2025年度):
-
電気自動車:最大85万円
-
プラグインハイブリッド車:最大40万円
-
FCV(水素自動車):最大250万円
-
-
加点条件:
-
V2H(Vehicle to Home)対応車:補助金が加算
-
太陽光発電との併用設置:最大20万円の追加補助
-
13年以上経過した車からの買い替え:一部補助条件で優遇あり
-
② 自動車重量税の免税・軽減(環境性能割)
-
新車購入時に課される重量税が、車種によって免税または軽減されます。
-
燃費基準を満たした車両であれば、最大100%免税(非課税)となるケースも。
③ 自動車税(種別割)のグリーン化特例
-
新車登録初年度から一定期間、自動車税が軽減されます。
-
13年以上経過車には15%の重課があるため、買い替えで軽減対象に切り替えると経済的メリットが大きくなります。
自治体の補助制度
各自治体でも、独自の補助金や優遇策を展開しており、国の制度と併用できる場合が多いです。ここでは代表的な自治体を例に紹介します。
東京都の「ゼロエミッション車導入促進事業」
-
対象:EV、FCV、PHEV(新車)
-
補助金額:
-
EV(普通車):最大60万円
-
EV(軽自動車):最大45万円
-
-
加点条件:
-
V2H設備導入:+10万円
-
都内で13年以上経過した車を廃車にする:+10万円加算
-
神奈川県のEV普及促進事業
-
EV新車購入時に補助(1台あたり最大30万円)
-
条件を満たせば都と合わせて90万円以上の補助を受けられることも。
愛知県:ZEV(ゼロエミッションビークル)導入補助
-
EVまたはFCV購入で最大40万円
-
地域の中小企業が事業用車をEVに切り替える際は追加補助あり
福岡市の次世代自動車導入支援
-
一般家庭でも利用可能
-
補助対象:EV/PHEV
-
補助額:最大30万円+自宅充電設備設置で追加補助あり
札幌市・仙台市・広島市など
都市によって補助額や対象が異なりますが、「車の年式」「排気量」「廃車の有無」などで優遇措置が変わる場合があります。公式サイトでの確認が必須です。
補助金は併用できるのか?
多くの人が気になるのが、「国の補助金と自治体の補助金は併用できるのか?」という点です。答えは「原則として併用可能」です。
たとえば:
-
国のCEV補助金(例:電気自動車で65万円)
+ -
東京都のゼロエミ車補助(例:EV普通車で最大60万円)
→ 合計125万円の補助が受けられるケースも。
ただし、自治体によっては「他の補助制度を受けている場合は対象外」となる場合もあるため、申請前に必ず条件を確認しましょう。
補助金の申請時期と注意点
補助金は「予算がなくなり次第終了」というケースが非常に多く、特に人気の高いEV車種や、東京都のような高額補助制度では、受付開始から数ヶ月で終了することも珍しくありません。
注意すべきポイント:
-
新車購入前に事前申請が必要な場合がある(後からでは不可)
-
廃車証明書の提出が必要な場合あり(13年超の車が対象条件)
-
リース車や中古車が対象外になる制度も多い
-
補助金の交付までに数ヶ月かかることもあるため、資金計画に注意
2025年時点では、国の「CEV補助金」や「環境性能割」などをはじめ、東京都・神奈川県などの自治体による補助制度が豊富に用意されています。13年超の車を廃車にしてエコカーに買い替える場合、最大100万円以上の補助金が得られる可能性も。制度は年度によって変動するため、最新情報を確認しつつ、賢く申請を進めましょう。
補助金をもらうための条件と申請手順を徹底解説
補助金が受けられると聞くと「申請さえすれば誰でももらえる」と思いがちですが、実際には細かい条件を満たす必要があります。また、制度によっては購入前の事前申請が必須なケースもあり、流れを誤ると申請自体が無効になってしまうリスクも。ここでは、補助金をスムーズに受け取るために押さえておきたい条件と、申請までの具体的な流れをわかりやすく解説します。
補助金の一般的な条件とは?
国や自治体によって異なるものの、多くの補助金制度では以下のような共通条件があります。
【1】対象車種であること
-
国のCEV補助金では、経済産業省が指定する車種リストに掲載された電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池車が対象です。
-
自治体の補助も同様に「〇〇市の認定を受けた車種であること」が求められます。
【2】新車であること
-
原則、中古車は補助対象外です。
-
一部の制度でリース契約の新車が認められている場合もありますが、個人契約での利用に限られることが多いです。
【3】13年超の車を廃車する場合は証明が必要
-
補助金の加点条件として「13年以上経過した車を廃車したこと」が求められる制度では、リサイクル券のコピーや使用済車両引取証明書などが必要です。
-
廃車から○日以内に新車登録すること、という時系列の制限もあるので注意が必要です。
【4】本人名義であること
-
申請者と車の登録者が同一でなければならない場合が大半です。
-
名義貸しや家族名義での申請は不可となるケースも。
【5】指定期間内に申請すること
-
「購入後〇日以内」「登録後〇ヶ月以内」など期限が設けられています。
-
申請漏れや期限切れによる不支給は自己責任となるため、必ず購入前からスケジュールを逆算して動きましょう。
申請手順の流れ(国の補助金を例に)
国の「CEV補助金」を例に、申請から受取までの流れを説明します。
ステップ1:車の選定・見積もり取得
補助金対象車かどうか、販売店に確認し、見積書を発行してもらいます。補助対象になるか不安な場合は、公式サイトで対象車両リストをチェックしておきましょう。
ステップ2:申請用のアカウント登録
CEV補助金の申請には、一般社団法人 次世代自動車振興センターの「申請ポータルサイト」でアカウントを作成する必要があります。
ステップ3:必要書類の準備・アップロード
-
車両の注文書・契約書
-
車検証(登録済みの場合)
-
リサイクル券や廃車証明書(13年超車を廃車する場合)
-
本人確認書類(免許証など)
すべての書類を電子化してオンラインでアップロードします。
ステップ4:審査と交付決定通知
申請内容が審査され、問題がなければ交付決定の通知がメールまたはマイページで届きます。これで補助金受給が「確定」となります。
ステップ5:補助金の振込(最長で4ヶ月程度)
交付決定後、最長で3~4ヶ月程度で指定口座に補助金が振り込まれます。繁忙期はさらに遅れることもあります。
自治体補助金の場合の注意点
自治体ごとの制度は申請ルールもバラバラです。以下の点に注意しましょう。
-
事前申請が必須:一部自治体では「購入前」に申請し、審査通過後に購入しなければ対象外になることも。
-
先着順・予算上限あり:人気エリアでは数ヶ月で受付終了する場合も。毎年4月〜6月が狙い目です。
-
充電器設置やソーラーパネル併用が条件の場合あり:特に東京都などでは、環境対策設備との同時導入が条件になるケースが増えています。
ディーラーに任せる vs 自分で申請
補助金の申請は、慣れていないと少し複雑です。ディーラーが代行してくれる場合もありますが、必ず「どの補助金まで対応してくれるのか」は確認しておきましょう。
-
ディーラーが対応できるもの:国の補助金(CEVなど)や大手自治体の補助金
-
対応してくれないことが多い:地方自治体独自の制度、小規模自治体の先着型補助金など
補助金をフル活用するには、申請可能な制度を自分でもリサーチすることが大切です。
補助金を確実に受け取るには、条件を満たす車を選ぶことはもちろん、購入のタイミング・必要書類・申請期限などを事前にしっかり確認しておくことが重要です。特に13年超の車からの買い替えでは、廃車証明の準備やタイミング調整が補助金受給のカギを握ります。失敗しないためにも、購入前に制度の全体像を把握し、スケジュールを逆算して動きましょう。
13年以上乗った車は本当に買い替えるべき?維持コストと買い替え時期の判断ポイント
13年以上乗ってきた愛車には、思い入れがあるものです。「まだ動くし、特に不便もない」と感じている方も多いでしょう。しかし、維持にかかるコストや将来的なトラブル、税金の重課を考えると、買い替えのタイミングを見直す価値があります。この章では、「今、買い替えるべきかどうか?」という視点で、長期所有車の経済的リスクや判断基準を整理していきます。
重課税・燃費・修理…長期保有車の隠れたコスト
13年以上経過した車の所有には、目に見えないコストがいくつもあります。
【1】重課税の影響
前章でも紹介した通り、13年を超えると自動車税・重量税が約15〜25%増加します。たとえば、排気量1.5Lの車を所有していた場合、年間の自動車税が約5,000円、車検ごとの重量税が約4,000円増える計算です。これだけで1台あたり年間1万円近い出費増となります。
【2】燃費の悪化によるガソリン代増
年式の古い車はエンジン効率が低下しやすく、同クラスの新型車と比べて燃費が2〜5km/L以上劣るケースも珍しくありません。年間1万km走行と仮定すると、ガソリン代だけで年間2万円〜4万円の差が出ることもあります。
【3】修理費の増加
年式が古くなるほど部品の劣化や故障が増え、修理費がかさみがちです。エアコン、パワーウィンドウ、ブレーキ系統などの修理には数万円単位の費用がかかることも。また、13年を超えると「部品供給が終了」してしまうケースもあり、車検に通らない・修理が長引くなどのリスクも出てきます。
維持費 vs 買い替え費用のシミュレーション
次に、維持し続けた場合と買い替えた場合のトータルコストを比較してみましょう。
ケース1:13年超の普通車(年間維持費)
-
自動車税(重課後):約40,000円
-
車検費用(重量税含む・2年で):約100,000円
-
修理費・消耗品交換:年間50,000円程度
-
ガソリン代(燃費10km/L・年1万km):約160,000円(@160円/L)
合計:約350,000円/年
ケース2:新車ハイブリッド車購入後(年間維持費)
-
自動車税:30,000円以下(軽減あり)
-
車検費用:初回は3年後、それ以降も軽量化+減税対象で安め
-
修理費:ほぼ不要(保証期間内)
-
ガソリン代(燃費20km/L・年1万km):約80,000円
合計:約150,000円/年
買い替えの初期費用(例:200万円)を10年で償却する計算でも、ランニングコストの差で年々トータル負担は逆転する可能性があります。
買い替えを判断する3つのチェックポイント
買い替えが「損」にならないために、以下の観点から自分の状況をチェックしてみてください。
【1】年間走行距離
年間走行距離が多い人ほど、燃費差によるコストメリットが大きくなります。年1万km以上走る人は、燃費の良い車にすることで数万円の節約が見込めます。
【2】今後の修理予定
「次の車検でタイミングベルト交換」「エアコンが効かない」「ブレーキから異音がする」など、今後の高額修理が予想されるなら買い替えが現実的です。20万円超の修理見積もりが出たら、買い替えを検討するラインと考えていいでしょう。
【3】補助金・税制優遇の有無
13年超の車を下取りまたは廃車にして、電動車に買い替えると補助金が加算されたり、税の軽減が受けられるタイミングがあります。国のCEV補助金や自治体の補助がある今は「買い替えの好機」です。
迷う場合は「車検前」が1つのタイミング
買い替えるかどうか迷っているなら、車検のタイミングが1つの分岐点です。次回車検にかかる費用と重課後の税負担を合算してみて、それを「頭金」に新車購入を検討するという視点を持つのもおすすめです。
また、車検前に売却すれば「買取価格」が少しでもつく可能性があります。車検を通してからでは査定額が下がることもあるため、タイミングも重要です。
13年以上経過した車を所有し続けることは、税金・燃費・修理費といった面で見えないコストが大きくなりがちです。買い替えを検討するタイミングとして、車検や大規模修理の前は絶好のチャンス。特に現在は補助金や税制優遇制度も充実しているため、「買い替えた方が得」になるケースが多く見られます。冷静に費用対効果を比較し、自分にとってベストな選択をしましょう。
まとめ|13年超の車は補助金と税制優遇を活用して賢く買い替えを
13年以上乗っている車を所有していると、愛着がある一方で、知らず知らずのうちに経済的な負担が増している可能性があります。税金の重課や燃費の悪化、修理費の増加など、長期保有車には“隠れコスト”がつきものです。特に日本では、国の「グリーン化特例」や「環境性能割」、さらには自治体のEV補助金制度などが充実しており、「古い車を買い替える」ことで税負担を軽くできる仕組みが整っています。
2025年現在、国が実施しているCEV補助金では、電気自動車やプラグインハイブリッド車に対して最大85万円の支援が行われており、東京都や福岡市など一部の自治体ではさらに数十万円の補助が加算されます。13年以上経過した車を廃車にして買い替えることで、これらの補助制度の“加点対象”になるケースもあり、補助金額が大きく跳ね上がる可能性もあるのです。
一方、補助金の申請には事前の準備が不可欠です。購入する車種が補助対象かどうか、購入タイミングと申請締切のスケジュールが合っているか、13年超の車の廃車証明書が提出できるかなど、いくつかの条件を満たす必要があります。とくに「知らなかった」だけで数十万円を受け取れない例もあるため、補助制度の内容は必ず購入前に確認するようにしましょう。
そしてもう一つ重要なのが、「本当に買い替えるべきか?」という視点です。経済的な面で考えれば、維持費と補助金、燃費性能の差を比較することで、将来にわたる“総コスト”を大幅に抑えられる可能性が高いのは確かです。さらに、近年のEV・ハイブリッド車は性能が向上し、充電環境や走行距離の面でも実用性が増しているため、「次の車」として十分に選択肢に入る時代になっています。
今の愛車が13年を超えている、または近づいているという方は、ぜひ一度、国や自治体の補助制度をチェックしてみてください。「まだ走るからもったいない」と思う気持ちもあるかもしれませんが、賢く制度を使えば、買い替えは“出費”ではなく“節約の一手”になることもあるのです。
【車を高く売るなら無料一括査定がおすすめ】
「ナビクル車査定」

参考:ナビクル車査定
一括査定サービスは低い査定業者と高い査定業者との買取査定額の差を比較することができます。ナビクル車査定は、最大10社から一括査定が受けられ、申込は簡単、申し込み後直ぐに愛車の概算価格がわかるので安心です。
「60秒ほどで、査定依頼が完了」
「最大10社へ査定依頼可能」
「複数社が競争して、相場が上がりやすい」
「最高の査定額の業者に、売れる」
「相場チェックとしても役立つ」
メールでの連絡を希望したい場合などには、総合窓口があり「ナビクルHP問い合わせ」から連絡すると一括査定を依頼した各業者にナビクルが希望を伝えてくれます。
複数の買取専門店に実際に無料出張査定に来てもらう事で、価格競争が起きやすく、査定額アップの交渉を有利に進められます。
できるだけ車を希望価格で売りたいのであれば、おすすめの一括査定サービスです。
数十万円高い査定額がつくことも!
車一括査定サイト ナビクルはコチラ>>https://a-satei.com/satei/navikuru/
▼愛車を高く売る無料申し込みはこちら▼

【中古車を探すならご希望の車をプロに依頼するのがおすすめ】
【ズバット車販売】
お得に中古車を買う方法は中古車販売店やディーラーではなく、品質のいい中古車をプロに探してもらうのもおすすめです。中古車選びを間違わなければ、車検付き、一括で買える品質のいい中古車も見つかります。
【あなたが見てる中古車情報 実は3割だけしか見れてない!?】
中古車はネットや店頭で探していると思いますが、実はこれ、全体の3割だけなんです。
残りの7割は業者しか見ることはできなかったのですが、
中古車お探しサービスにリクエストすると、中古車のプロがあなたに合ったとっておきの1台を探し出してくれます。
無料のサービスなので中古車を探している方はぜひ、活用してください!
中古車お探しサービスはコチラ>>https://www.kuruma.zbaboon.jp/
ここでしか探せない非公開の中古車もありますので
毎日更新されるクルマの情報を逃さないようにしましょう!
▼ズバット車販売!無料登録はこちら▼